ハム遙夏しま2021・01
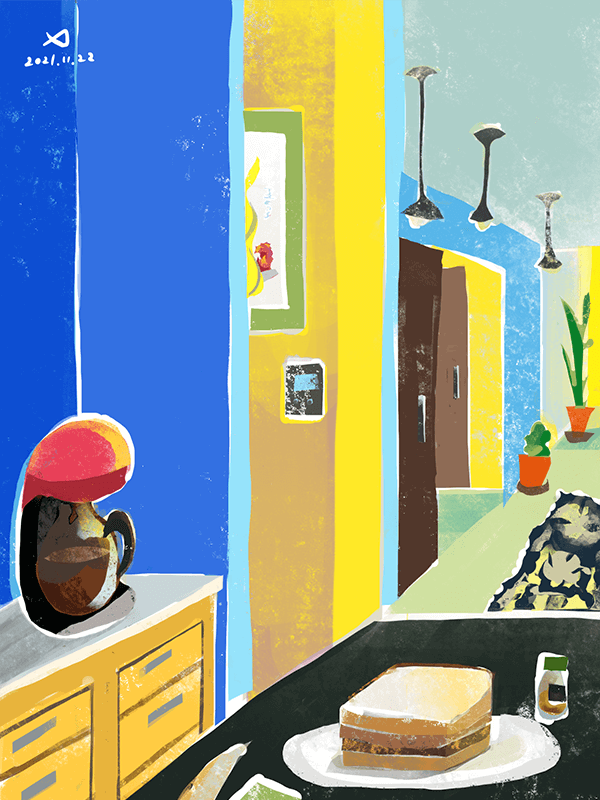
朝、お風呂に入っている。たまに朝、入りたくなる。お風呂に入って耳まで浸かると換気扇の音がさっと消える。ざぶんごぶごぶごぶと耳のまわりにお湯がはりつく。耳はいつもわたしの理性に雑多な現実を繋がせている。だからこうすると一瞬にして現実のアレコレが一時停止できて便利だ。シャットアウト。お湯の中で眠気を落とし、膝を抱えたわたしはぱっちりと目を開ける。そのままただ天井を見て呼吸をしているだけの存在になる。とても快適だと思う。わたしは湯船に潜るこの時間が大好きだ。
よく湯船に潜った状態を胎児に戻ったなんていう人がいるけれど、その表現はあまりピンとこない。わたしにとって湯船に潜るのは自分自身に限りなく近づく手続きだ。向き合う必要はない。ただ天井を見ていればいい。鏡と向かいあったり、ブログに日記をしたためたり、なんでも言い合える親友をつくったりなんかするより、はるかに今のこれが自分に近くなれる。そんなふうに思っている。
お湯のごぼごぼが落ち着く。右耳からつつと小さな空気が出ていく。温かい静けさをわたしは手に入れる。変な角度で体育座りをする自分自身の隣にわたしは座る。さあお風呂のお湯が外の世界を片付けましたよ。嘘も見栄も駆け引きも不要です。話してごらんなさい。そう自分自身の肩をたたく。そこまでやると、わたしはゆっくりと思考を始める。
距離感について考える。
大学の基礎科目の講義で社会学の教授がこういっていた。
「この40年、私たちはインターネットが生まれて発展するとともに、相手との距離感のタガを外してしまいました。身近な誰かには目もくれず、顔の知らない相手へプライベートをさらし、遠い世界の相手に拳を握ったり刃を向けたりもする。その歪みかたはまるで巨大な万華鏡のなかに入って人と対峙しているかのようです。今や人間関係というものは、時代に類を見ないちぐはぐな現象になっています」
その説明を聞きながら「タガが外れる」とわたしは心の中で復唱した。タガか、タガね。外れてるのか。生まれたときからインターネットがあって、ネットを通して人と生きているわたしは、そもそも教授のいう歪んでいない人間関係を知らないんだけれど。タガは最初から外れてるってことだよね? 今、いっしょに講義を受けている友人とか、小中高と仲良くやってきた友達とか、とくに仲良しってわけでもないけど別に嫌いあってるわけでもない、わたしの両親や兄弟とか。携帯でメッセージ送るけど。写真とか見せ合うけど。近況とかSNSにあげるけど。これ、彼らとわたしは十何年もちぐはぐな人間関係を形成してきたってことで合ってる? いや別にふつうだよ。ふつうなんだけど……?
お湯のなかで触る髪はいつもより太く、コシがあるように感じる。水分を吸って太くなっているのだろうか。海藻みたいにふよふよと流れる髪を、耳にかからないように指ですく。
ネットによって変わった距離感のことを考えてみる。
ネットがなければ、友人、知人、家族すべてで連絡の頻度はかなり減るだろう。つまり今はネットがないときより、たくさん連絡をするから距離が近いといえる。教授は「身近な誰かには目もくれず」といった。だいぶ違う気がする。ネットが身近な人への無関心につながっているとは到底思えない。連絡できるから、ありがたみが減っているとかそういうことだろうか。
SNSで知らない人をフォローしている。有名人とか。音楽情報に強い人とか。ありがたいとは思う。向こうが望めば良く応じてあげたいとは思う。でも実際コメントをやりとりしたことなどない。だって他人だ。距離感、他人。友人もフォローしている。これはもちろんコメントする。適当な会話。お喋りだ。距離感、友人。
ちぐはくだろうか。そもそもフォローするしない。それで相手との何が変わるのだろうか。そんなもので変えられる何かがあるのだろうか。わたしにはピンとこない。
わたしにとってネットは結局、あれば便利で、なければ不便で、そんなものだと思う。このツールがわたしのタガを外すなんて、そんなこと大それている。たしかにネットのあるなしで、きっと生活に多少の違いはあるんだろうけれど、それが教授のいう人間的ちぐはぐさを生み出すとは思えない。
相手との距離。
Distance.
それのタガ……ねぇ。
教授には悪いけど外れてなんかないと思う。あの先生はきっと古い時代の人だからネットってものに、きっとまだ夢を見てるのだ。インターネットがすべての人を繋ぐ、みたいな。そんなことは起こらない。そんなことは表面的な見えかただけだと思う。わたしたちはたしかに繋がれるし、一見、自由気ままに繋がっているように見える。フォロー、フォロワー。ライク、メンション、ファボ、ポスト、ストーリー。機能を見れば人間関係はいっしょの体裁だ。でも実際は相手とのあいだに目には見えない色違いの透明な膜が張られている。友人と有名人、家族と音楽情報をくれる人。それぞれに用意される膜はまったくの別物で、それは画面と自分、画面と相手との間にきっちり存在している。
ざばりとお湯から顔をあげる。わたしを現実から隔てていたごぼごほがきれいに耳元から消える。同時に今、考えていたことをわたしは忘れる。体からお湯に出して、お風呂の栓を抜いて流し、過去のことにする。ひととおり考えた気もするし、別にどうだっていいことだ。
シャワーで軽く流してお風呂を出る。濡れた髪を乾かして、キッチンへいく。携帯から小さめのボリュームで音楽を流す。アコースティックギターで始まるラップ調の曲。少し渋めの枯れたボーイズヴォイス。「Yo Yo――」首を揺らしながらケトルを火にかける。コーヒーを淹れるためにお湯を沸かすのだ。「サンドウィッチつくるね」と寝室の母に声だけかけておく。「ありがと、早いね」と母が返す。うんとだけわたしはいうとキッチンへ戻る。ベランダに光が差している。
トースターに食パンをセットする。
レタスを洗う。
トマトは輪切りにする。
キュウリも薄く切る。
ベーコン……はないのか。
ハムならあった。焼く。
目玉焼きも。
母が起きてきてコーヒーを淹れてくれる。キッチンに香ばしい匂いが充満する。トースターがちんと鐘を鳴らす。パンの焼けた香り。一日が始まるって感じがする。トーストにバターを塗る。忘れてた。マスタードとマヨネーズも冷蔵庫から取り出す。
「なに、サンドウィッチ、お弁当にするの?」母がいう。そうだよと答える。「大学で友達とランチするの」わたしは何ごともない風にいう。母は興味なさそうにふーんとだけいって、自分の分のコーヒーだけサーモマグに注ぎ、さっさとダイニングテーブルで飲んでいる。このあとすぐ父と弟が起きてきて母は慌ただしくなる。だからわたしは彼女になにも言わない。「いい天気ね」母はひとりごとのように呟く。ラップ調の曲は流れ続けている。Yo Yo Yo――機嫌の良いハミングヴォイス。そうだねいい天気だねと心の中で返事して、わたしは小さめに首でリズムをとる。
ふとさっきお風呂で考えた膜のことを思い出す。自分に張り付く膜のことと、相手に張り付く膜のこと。ネットはわたしたちを繋ぐけれど情報がその膜を不用意に越えてこちらにくることもないし、あちらにいくこともない。越えさせるのはわたしだし、相手だ。
いろいろな膜がすべての人にまとわりついている風景を想像する。薄く透けた膜たちを体から少し浮かせたところにピタリと張って、みんなが街中を歩いている。ピンクやライムやレモンイエロー……カラフルなそれは、彼らの空気感を守り、同時に彼ら自身を定義している。
わたしたちは膜を通してコミュニケーションする。相手を受け入れるため、相手に受け入れてもらうため、場合によってはゆっくりと自分の膜を取り除こうとする。膜の継ぎ目を目で追い、合理的なほころびを探し出す。あるいは相手を遠ざけるため、その膜を厚く自分に張ることもあるだろう。関係の違い。
相手の膜を操る術はおそらくない。それはあくまでわたしや相手の膜であり、意識的なこととは違う階層でとりおこなわる操作だろうから。相手の膜を操ろうと考えることはおそらくかなり危険な思想だと思う。
マグカップにコーヒーを注いで一口飲む。おいしい。ふうと息が出る。半分飲んだら残りは牛乳を温めてラテにしようか。わたしは牛乳を鍋にかけ、それからサンドウィッチの具材を挟みに取り掛かる。
まな板の上にバターを塗ったトーストを置く。そこにレタス、ハム、キュウリ、トマトとのせていく。その上に目玉焼き。マスタードとマヨネーズを塗って、軽く胡椒をふり、トーストでふたをする。慎重に半分に切って……ひとつ完成。目玉焼きのあら熱がとれてからラップに包もう。
これをあとみっつとお弁当用にふたつかな。
膜がとっぱらわれたとき、人はタガを外すのだろうか。わたしは想像する。膜。それこそが教授の言うちぐはぐな人間関係へつながっている気がする。膜の在り方というか状態というか。もしかすると膜の非対称さが歪みを生むのかもしれない。
例えば自分だけが膜を外して相手を受け入れるつもりで、相手の方には膜が張ってあったり。その逆で、こちらは分厚く膜を張っているのに、相手が内側へ入って来ようとこちらの継ぎ目を探してきたり。そういう状態を認知したとき人はいともたやすく己のバランスを失うように思う。そもそもどちらかの膜が見えない人がいるのかもしれない。膜盲目。
弟や、父と母にもその膜は張っているのだろうか。恐らくそうなのだろう。互いに膜を張り合っている。わたしたちは膜に包まれざるをえない生き物なのだ。その膜こそがわたしたちを自分自身として冷静に保っているから。距離感という言葉を借りるなら、その膜は人間関係の最後の距離なのかもしれない。母が好きな宇多田ヒカルの「Final distance」という曲を思い出す。
――I wanna be with you now.
牛乳がわく。鍋にうっすらと膜が張っている。ここにも膜。膜のことばかり考えているなとわたしは少し自分を笑う。サンドウィッチの具材、これも膜といえば膜だな。レタス、トマト、ハム、キュウリ。パンとパン、具材をそれらを仕切って味わいをつくっている。具材によって遠ざかるパンとパン。膜が距離をつくる。でも仕方ないよ。サンドウィッチがおいしくなるためだもの。仕方ない。あぁ織姫と彦星。
「……いや、ちがうか」
パンは別に遠ざかっていないな。サンドウィッチになったことで個別の存在だったパンがひとつになっているもの。パンは具材によって引き離されたのではなくて、具材によってひとつに繋がったんだな、この場合はきっとそうだ。どんな具材で間に膜をつくるか、それでパン同士のありかたが変わって、サンドウィッチのおいしさも変わるわけだ。わぁ素敵じゃないの。
わたしはマグカップに牛乳を足してラテにする。「なんか言った?」と母がいう。ひとりごとだよ、とわたしは答え、サンドウィッチの具材の挟みかたを悩んだのと、適当ないいわけを並べる。「なんだっていいじゃない」と母は笑い、わたしはまあそうなんだけどさ、と言う。
どんなに穏やかに静かな朝でも時間は確実にへって、その場から去っていくのをわたしは知っている。あと15分もすれば弟と父が起きてくる。朝食の支度が本格的に始まり、家がバタバタとして、流されるようにわたしも家を出て、電車に乗り、あんまり将来に関係のなさそうな二限の講義を受けにいく。そしてそのあと友達とランチをする。
そうだ、相手の膜を操作する術……。
あるなと思う。相手の膜のかたちを変えるために、自分の膜を捨て去るのだ。膜を失くすことで人は自分自身の定義を見失う。体が膜の外にあふれだし、この煩雑で雑多な世界に流れ出す。わたしの境界が外へ外へふくらみ、わたしという存在は薄められていく。わたしは自分を見失い、いったいどこからどこまでが自分で相手なのか、まったく感知できなくなる。膜盲目。教授のいうタガってやつが外れて歪んでいく。
しかしそれでもわたしは膜を失うことによって一枚分、相手の膜へ近づける。そして外れたタガによって相手のそれを、さも自分のそれだと思うことができる。相手が自分になり、そのとき彼の膜をわたしは手に入れる。それを操作して……いやわたしはなにがしたいんだ?
「わけわからん」
母が「なにが?」と聞き、いや今日の講義の課題のこと、と答える。わたしはサンドウィッチをあらかじめ作ろうと思った人数分、きっちり作る。最後のサンドウィッチを作るとき、何が変わるわけでもないのだろうけど、わたしは多めにいれる予定だったハムを一枚だけにして、ほんのわずかに薄いものを作った。マグカップにいれたラテはまだまだ熱いままだ。母は読みかけの本を読んでいる。「先食べちゃう?」と言って、わたしは自分と母の分のサンドウィッチを皿に盛るとダイニングテーブルへ持っていく。